評価方法について
審査方法は主にスコア化と選出理由の可視化を行います。
審査の基本的な基準として以下の回答とさせていただいております。
1. 作品評価の基準について
作品+プレゼンを総合的に評価する
- 設計力だけでなく、伝える力や考えの整理も重要な要素とする。
- 本選では出展者とクリティークでの対話が特徴であるので、プレゼンも評価に入れたい。
- 「自分の設計の魅力を伝えられる=事前準備が万全である」のため評価に入れる。
2. 学生自身の理解と評価の関係
学生が自分の作品の価値に気づいていない場合の評価は?
- 気づいていないなくても評価は下げない。
講評者が新たな価値を発見した場合の扱いは?
- 設計者の意図に関係なく、発見された価値を評価する。
3.卒計展の目的と方向性
(サブ的目的)最優秀者を決める「競争の場」とする
- 作品+発表を総合的に評価し、最も優れた学生を選ぶ。
- 大会として盛り上がるための1つの手段
(重要)優れた建築のアイデアを抽出する「提言の場」とする
- 設計者個人ではなく、作品の意義や価値を重視する。
- 400人(案)のなかから未来の建築を考えてゆく優れた案や方針を抽出して、それら全体が400人の学生の世代的メッセージである
- 1995年DesignReviewの目的3つ
1.現代建築、都市を取り巻く諸問題を議論し、福岡の建築批評のレベルを高める。
2.学生の建築作品の批評を通じて、大学での設計教育のあり方を考える。
3.この活動を広く一般に公開し、大学と社会との情報交換の場を提供する。
1995年当時の運営は先生によるものであり、今のDesignReviewとは状況も違うが、大会の目指すところは変わっていないのではないか、と考えこの3つを提示する。
4. 教師と学生の関係性
卒計展が「指導の場」になるべきか?
- 学生へのフィードバックの場として機能させる。


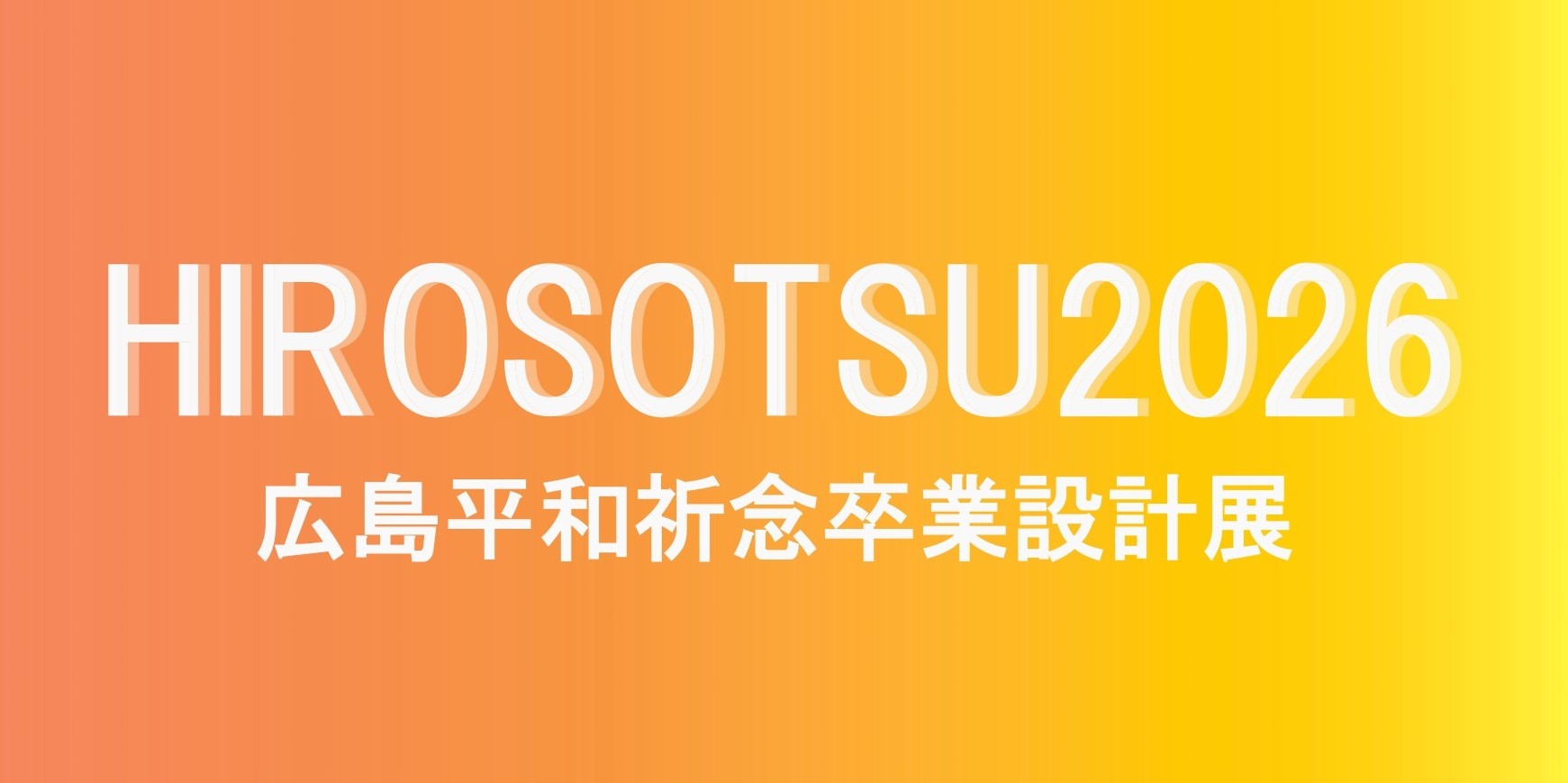


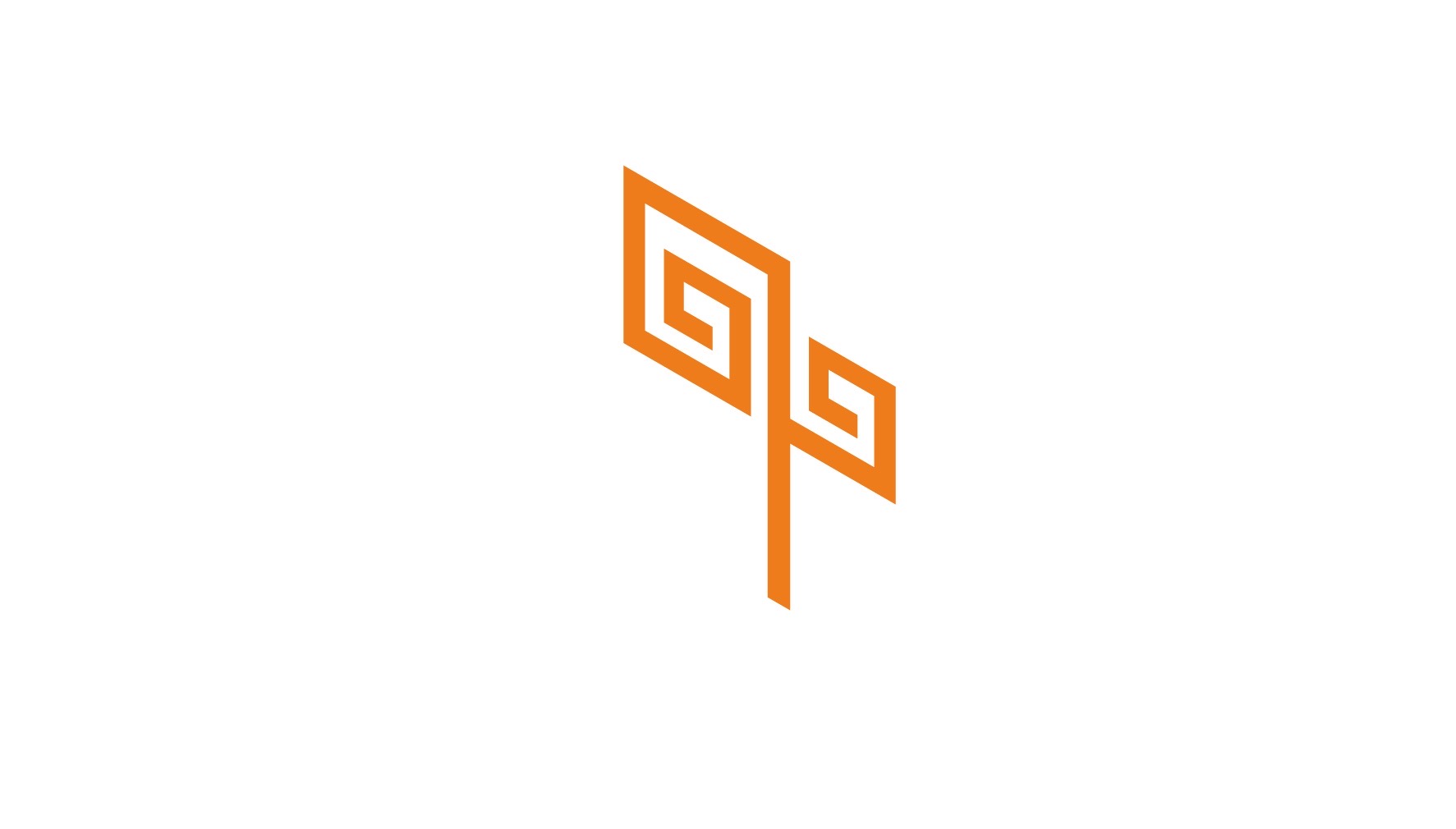
-2-scaled.png)
-2-1-scaled.png)
.png)
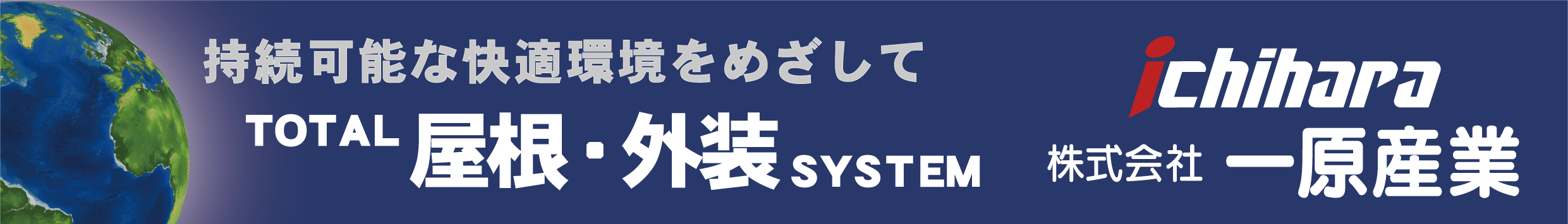


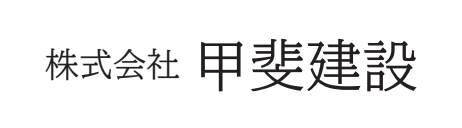

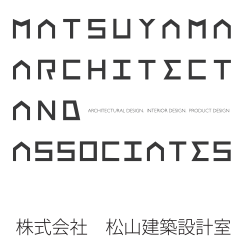


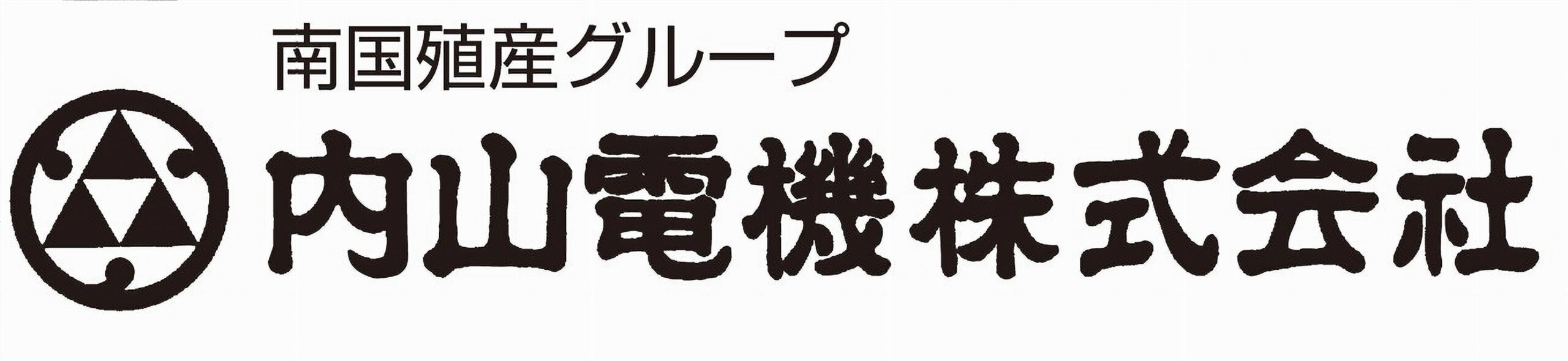




カラー_page-0001.jpg)



